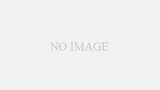「睦月」「如月」「弥生」――日本の旧暦に由来するこれらの美しい月の名前を、皆さんはご存じでしょうか?
しかし、すべてを正しく覚えるのはなかなか難しいものです。
本記事では、旧暦の月の和名をスムーズに覚えられるよう、意味や由来を詳しく解説しながら、簡単に暗記するコツをご紹介します。
語呂合わせやイメージ法を使い、楽しく覚えられるよう工夫していますので、ぜひ最後までお付き合いください。
また、日本の伝統的な行事や風習と関連付けることで、より身近に感じることができるでしょう。
旧暦の月の和名とは?その意味と由来を解説

日本の暦には、現在の「1月」「2月」といった新暦の呼び方とは別に、旧暦に由来する「和名」が存在します。
これは、かつて使われていた太陰太陽暦に基づく月の名前であり、それぞれの時期の気候や自然の変化、習慣などに由来しています。
例えば、1月の「睦月(むつき)」は、新年を迎えて家族や親族が睦まじく集うことにちなんでいます。
このように、各月の名前には古来の日本の文化や風習が反映されているのです。
また、これらの和名は日本文学や詩歌の中にも登場し、昔の人々がどのように季節を感じ、暮らしていたかを知る手がかりにもなります。
例えば、古今和歌集や万葉集の中には「長月」や「神無月」などの表現が見られ、それぞれの時期の自然や行事を詠んだ歌が数多く残されています。
旧暦と新暦の違い:月和名が生まれた背景
旧暦(太陰太陽暦)は、月の満ち欠けを基準にしていたため、1年の長さが現在の太陽暦(新暦)とは異なり、季節のずれが生じることがありました。
そのため、旧暦の月和名が表す時期と、新暦の1月、2月といった月の対応が完全には一致しないこともあります。
例えば、「師走(しわす)」は旧暦の12月ですが、現在の新暦では1月中旬ごろにあたる場合もあります。
この違いを理解することで、月和名の意味がより深く納得できるでしょう。
また、旧暦では「閏月(うるうづき)」が導入され、約3年ごとに閏月を設けることで、太陽の運行に近づけていました。
このため、現代のカレンダーとは異なり、毎年同じ日に特定の行事が行われるわけではなく、旧暦をもとにした祭りや伝統行事の日付が年ごとに変動することもあります。
各月の和名とその覚え方
1月:睦月(むつき)
「睦まじく集う」ことから名づけられた1月。
家族が一堂に会するお正月のイメージと結びつけると覚えやすいです。 また、新年の祝いとして行われる「おせち料理」や「初詣」と関連付けることで、より強く記憶に残るでしょう。
2月:如月(きさらぎ)
寒さが厳しく、衣を更に重ねる(「衣更着(きさらぎ)」)ことに由来します。
寒さ対策の重ね着を思い浮かべると覚えやすいです。 また、この時期には「節分」や「立春」といった行事があり、春の訪れを意識するとより印象に残るでしょう。
3月:弥生(やよい)
「弥(いや)生い茂る」、つまり草木が生い茂る季節を表します。
春の訪れとともに、自然が活気づくイメージで記憶すると良いでしょう。 また、ひな祭りが行われる月でもあり、「桃の節句」と関連付けるのもおすすめです。
4月:卯月(うづき)
「卯の花が咲く時期」から名付けられたとされています。
この時期は桜が散り、初夏の訪れを感じさせる花々が咲き始めます。
特に、卯の花は純白の美しい花として知られ、古くから和歌にも詠まれています。
春の風景を思い浮かべながら、「卯の花=4月」と関連付けると記憶しやすくなるでしょう。
5月:皐月(さつき)
「早苗を植える月」であり、田植えの季節を表します。
この時期、日本各地の田んぼでは、農家が一斉に苗を植える風景が見られます。
また、皐月には「皐(さつき)」という言葉自体に神聖な意味が含まれ、神事に関連する植物の名としても使われていました。
田植えの風景を想像しながら、その歴史的背景も併せて覚えるとよいでしょう。
6月:水無月(みなづき)
「水の無い月」と書きますが、実際には「水を田んぼに張る月」という意味です。
この頃には梅雨入りし、各地でまとまった雨が降ります。
「水無月」という名称は、かえって水に満たされる季節を強調する表現だとも言われています。
また、京都では「水無月」という和菓子を食べる風習もあり、甘味と一緒に覚えると印象に残りやすいです。
7月:文月(ふみづき)
「書物を読む月」であり、七夕の短冊に願いを書く風習と関係があります。
平安時代の貴族はこの時期に詩や歌を書き交わし、学問に励む時期とされていました。
また、短冊に願いを書く七夕の習慣が「文(ふみ)」に由来するとも言われます。
学問や願い事を思い浮かべると、簡単に覚えられるでしょう。
8月:葉月(はづき)
「葉が落ちる月」であり、秋の訪れを感じさせる名前です。
しかし実際には、旧暦の8月はまだ夏の暑さが残る時期です。
この名は、山々の葉が落ち始めることからついたとされます。
紅葉し始める情景を思い浮かべると、自然と記憶に残るでしょう。
9月:長月(ながつき)
「夜長月」が由来とされ、秋の夜が長くなる時期を表します。
秋の涼しい夜を楽しみながら、月を眺める風習があったため、名付けられたとも言われます。
また、平安時代の貴族たちはこの季節に「月見の宴」を開き、和歌を詠み交わしました。
夜が長くなることを実感しながら覚えるとよいでしょう。
10月:神無月(かんなづき)
「神々が出雲に集まるため、全国の神々が不在となる月」とされています。
一方、出雲地方では「神在月(かみありづき)」と呼ばれます。
出雲大社で行われる神事と結びつけて覚えると、より印象に残りやすいです。
11月:霜月(しもつき)
「霜が降りる月」であり、冬の到来を感じさせます。
紅葉が終わり、朝霜が降りるようになるこの時期は、冬支度を始める季節でもあります。
冷え込む朝の光景を想像すると、覚えやすくなるでしょう。
12月:師走(しわす)
「師(僧侶)が忙しく走り回るほど忙しい月」とされます。
年末の慌ただしい雰囲気をイメージすると覚えやすいです。
また、この時期は大掃除や正月準備が進むため、「走るように過ぎる月」という意味も込められています。
語呂合わせで覚える月和名:効果的な暗記法
「むかし、きよい うさぎが さむい ふみ は ながい かみ しも しわす」 (睦・如・弥・卯・皐・水・文・葉・長・神・霜・師)
語呂合わせを使うことで、月和名をより効率的に覚えられます。
また、リズムに乗せて繰り返し唱えることで、自然と記憶に定着しやすくなります。
さらに、歌やイラストを用いた学習方法も効果的です。
例えば、和風の童謡に合わせて歌いながら覚えると、記憶の定着率が上がります。
また、各月の風景や象徴的な行事を描いたイラストと組み合わせることで、視覚的にも覚えやすくなります。
月和名を学ぶ際の注意点とポイント
- 旧暦と新暦の違いを意識する。
- 語呂合わせやイメージを活用する。
- 実際に書いて覚えることで記憶を定着させる。
まとめ:月和名を覚えて日本の文化を深く知ろう
月の和名は、日本の風土や文化、歴史と深く結びついています。
単に暗記するのではなく、それぞれの名前の由来を理解し、イメージしながら覚えることで、より楽しく学ぶことができます。
この記事の方法を活用し、ぜひ旧暦の美しい月名を自分のものにしてください。
また、旧暦を活用したカレンダーや、和風の手帳を活用すると、日常の中で自然と月和名を使う機会が増え、より親しみを感じることができるでしょう。
さらに、四季折々の日本の文化に触れることで、より深く月和名を理解することができます。
例えば、神社やお寺で行われる伝統行事に参加し、実際に和名の月にちなんだ習慣や風習を体験すると、自然と馴染みやすくなります。
ぜひ、月和名を覚えることを通じて、日本の歴史や文化への理解を深めてください。